ベンチャー企業と一言でいっても、その実態を詳しく解説した情報はなかなか見つけることができませんよね。
そもそもベンチャー企業とひとくくりにしても、内情は会社によってバラバラです。転職活動をする際に「ベンチャーに入社するか、大企業にいくか」は重要な決断ですよね。
そんな悩みの解決が少しでも解消できるようにまとめてみました。
この記事の読了目安時間 7分
ベンチャー企業を取り巻く環境はカオス!?
ベンチャー企業は3つのフェーズに分けられる
まずそもそもベンチャー企業とは何を指すのでしょうか?
ベンチャー企業とは、リスクを恐れずに挑戦する企業を指した和製英語です。海外ではStartup-businessと呼ばれます。日本でもベンチャー企業のさらに前段階として「スタートアップ」と呼ばれるフェーズの会社もありますね。
最近のベンチャー企業はその大半がITを使ったビジネスを展開していますから、Web関係の知識を習得することは必須です。
日本企業の99%は中小企業が占めているため、ベンチャー企業が日本経済を支えているという言い方もできるかもしれません。
規模が大きいメガベンチャー
明確な定義はありませんが、スタートアップフェーズを経て大きな規模となった企業を指します。DeNAや楽天、最近だとメルカリやSansan、ラクスもメガベンチャーといえるでしょう。株式上場しているケースも多く、人数も多いのが特徴ですが、日系大手企業と比較して【実力主義】【変化を好む】【意思決定の速さを重視する】など様々あります。
成長過程にあるミドルベンチャー
従業員数百名程度のベンチャー企業です。ある程度組織としての統制がとれていて意思決定の速さやクオリティ、攻めの姿勢を崩していないのがこのフェーズです。
代表的なケースでは上場企業のSpeeeやココナラなどがあげられるでしょう。
創業間もないアーリーベンチャー(スタートアップ)
従業員数名〜200名程度のシード期にあたるフェーズです。創業間も無い企業のことを指し、会社が持つプロダクトやサービスもPDCAを回しながら常にアップデートさせているような状態です。0→1のフェーズなので、全てを自分たちで作り上げていく覚悟が必要ですが、それを楽しいと思えるかどうかが重要です。
不安定な環境を生き抜くベンチャーはこれからの時代生き残る?!
筆者は新卒の就職活動で大手企業しか見ていませんでした。現在転職活動中のあなたはいかがでしょうか?
もちろん大企業が悪いとは全く思いませんし、実際私も新卒で大企業に就職したからこそ、社会の仕組みや大企業の内部事情などを知ることができたと思っています。
しかしその一方でベンチャー企業へ就職する面白さがあります。
それは、[ベンチャー企業は不安定だから]です。不安定な環境を生き延びるために考え続けたり、変化が激しいからこそ世の中の情勢を見極めて自分たちを変化させていく必要があります。そうしたマインドやスタンスは、今後の不安定な日本を生きていく上で最も重要なことなのではないかと考えています。不安定な環境を生き延びるからこそ、不安定な時代に対応できる安定さを持ち合わせる、ということです。
ベンチャー企業と大手企業は組織として全く違う
年功序列か実力主義かで分かれる
日系の大企業のほとんどは、その会社の中で年次を重ねていくにしたがって昇給・昇格していく[年功序列型]です。筆者の前職でも、入社後毎年横一列で昇給があり、入社4年後にはほぼ全社員の役職が一律アップしました。年収の差がでるのは営業実績から算出される賞与のみ、という状況でしたので、同期の等級はほぼイコールです。
大きな時代の流れとして、ジョブ型雇用が浸透してきたこともあり、年功序列の給与体系から脱却を図ろうとしている企業も出始めていますが、まだまだこのような年功序列で年収テーブルが設計されている企業は多くあります。
一方で、[実力主義][成果主義]で年収や等級が決定するケースが多いのがベンチャー企業です。ベンチャー企業はその多くが、いわゆるジョブ型雇用を取り入れているため、その人のスキルや成果にフォーカスして報酬を与えるという設計を組んでいます。頑張った分だけ、または成果を出した分だけ正当に評価してもらいたい!という方にはベンチャー企業があっているケースが多いと言えるでしょう。
業務の権限はベンチャーの方がもらえることが多い
業務権限はベンチャーのほうが圧倒的にもらえるでしょう。これはよく言われることですが、大企業とベンチャー企業の両方を経験した筆者が自信を持ってお伝えできます。
大企業は人数が多く、連動して部署も多いため業務がとてもセクショナリズムになっていて縦割りです。自分が抱える業務において、上流工程や下流工程は別の部署が担当するということは多いです。ですが、特にアーリーベンチャーやスタートアップ企業となると、少ない人数で会社を運営していかないといけません。その分、業務を分ける余裕などはなく、会社の備品の発注から経営に関する意思決定の近くまで携われる可能性を秘めています。
ベンチャーに集まる仲間は上昇志向が強い
お伝えした通り、備品発注などの細かい業務から、経営に関する意思決定まで幅広い業務を担当します。これは言い換えると『会社運営に関するスキル』が早期に身につきますので、それを求める人たちも自然と集まりやすいです。将来的に起業を考えている人は向いていると言えるでしょう。
将来起業したいならベンチャー企業への就職をするべき
ベンチャー企業へ就職するメリットを3つお伝えしたいと思います。
すべてを自分が主体となるという覚悟で仕事ができる
裁量権の大きさは、責任がついて回ります。責任を取る覚悟があるからこそ、大きな仕事に挑戦できる土壌があるのです。
組織の人数が少ないケースが多いので、大企業であれば部長がやるような仕事であったり、10名単位で動くようなプロジェクトもベンチャーであればイチプレイヤーが主導して成功まで導きます。逆に失敗したときも、全て「自分の至らなさが招いた結果である」と真摯に受け入れ、PDCAを高速で回していく覚悟が求められます。
結果を出せば社会人1年目からマネージャーになれる
新卒1年目であっても、プロジェクトを成功に導いたり、業務の垣根を超えて視座高く仕事をしていれば、経営陣からも信頼されやすい距離にいるのがベンチャーの醍醐味の一つでしょう。信用されれば、早くて社会人1年目からマネジメントを任されることもあります。
私が在籍していた大企業では、マネジメント層になるには最速で入社8年目からでした。どんなに優秀であっても、年功序列の会社に就職すると、早くからのマネジメント経験などは積めないでしょう。
経営者の見ている視界を知ることができる
会社を経営したいのであればベンチャー企業、特に創業間もないスタートアップ企業へ就職するほうが良いでしょう。
理由は単純で、経営者の近くで仕事ができるからです。
社長がどんな思いで会社を創業したのか、どんな手法でサービスやプロダクトを大きくしていくのか、どんなビジョンやミッションを持っているのか。考え方や思い、そして経営手法を近くで見ながら勉強することができます。
大企業の社長はそう簡単に会えません。筆者の前職では、代表取締役社長や会長が在籍していましたが、アポイントを取得する場合には秘書を通じてしか会えませんでした。しかも、一般の従業員がアポイントなんて取れませんので、月に1度開催される経営陣向けの報告会で対面するしかありません。経営陣がどういう情報にアクセスして、何を考えているかはわかりづらい構造になっています。
さいごに
いかがでしたか?
今回はベンチャー企業に就職するメリットを解説しましたが、決して「ベンチャー企業のほうが大企業よりも絶対に成長できる」ということではありません。
大事なのは、あなたが将来どうなりたくて、いまどういうことをやる必要があるのか、またはやりたいのか。そこをしっかり考えた上で、将来的に起業をしたいと考えているのであればベンチャー企業へ就職するほうが良いでしょう。
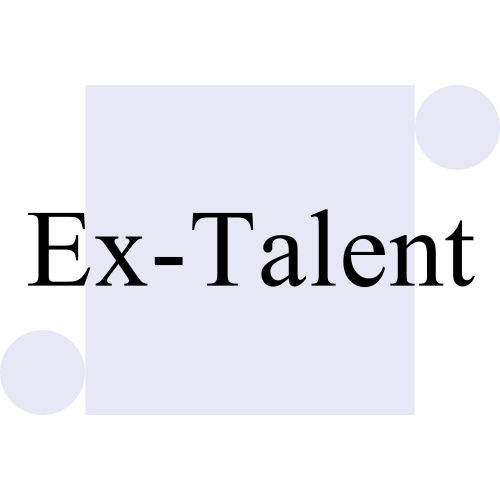


コメント